親族とフォト+会食のシンプルウェディング!ポイントや流れを徹底解説
はじめての方へ | 公開: / 更新:

結婚式はやりたくないとお考えの方に、ぜひおすすめしたいウェディングスタイルがあります。
それはフォトウェディングをされてから、親族や親しい友人を招いた少人数で会食を行うことです。
本記事では、『フォトウェディング+会食』のウェディングスタイルについて詳しくご紹介します。
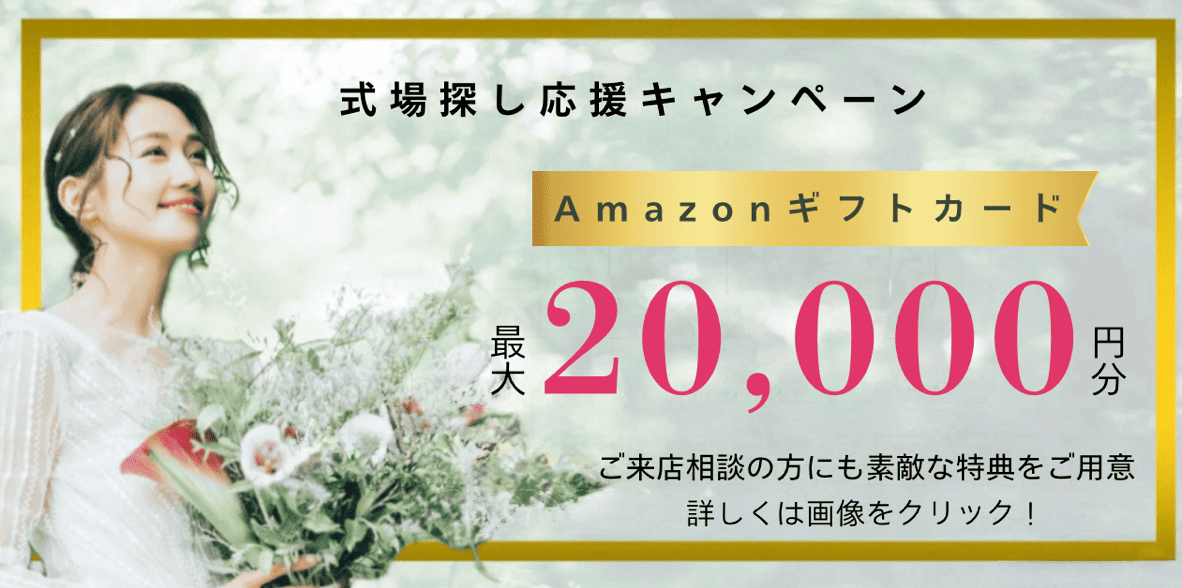
フォトウェディング+会食(食事会)で感謝を伝えよう
結婚式に対する考え方は人それぞれです。
カップルの数だけ、結婚式に対する思いがあると考えても良いでしょう。
ここでは、「挙式セレモニーに恥ずかしさを感じる」「再婚同士の結婚だから結婚式は…」「結婚式だけにお金をかけたくない…」「妊娠が分かったから結婚式は難しいかも…」といった様々な理由から結婚式に抵抗を持っている方へおすすめの方法をご紹介します。
その方法とは、
新郎新婦のふたりでフォトウェディングを行ってから、親族や親しい友人を招いて少人数で会食を行う『フォトウェディング+会食』です。
ふたりは結婚式が恥ずかしいと思っていたとしても、家族はふたりの晴れ姿を見たいと思っていることでしょう。
結婚式の機会を逃すと、相手の親族との接点はなかなかないものです。
婚礼衣装で撮影をしますので、プロのヘアメイクで美しくドレスアップをし、撮影した後はその衣装姿のまま、ご家族や親しい友人との会食をしてみてはいかがでしょうか。
フォトウェディングとは?魅力を教えます
挙式や披露宴を行わずに、婚礼衣装を身にまとった新郎新婦が写真を撮ることをフォトウェディング(フォト婚)と呼びます。
フォトウェディングは、立派な結婚式スタイルの一つです。
結婚式を挙げるふたりが結婚式より前に撮影することを「前撮り」、結婚式後の撮影を「後撮り」と言いますが、フォトウェディングは撮影自体が結婚式と同様の扱いになります。
挙式や披露宴をしない結婚式といったイメージで、ふたりだけではなく家族や友人のフォト参加も可能です。
フォトウェディングは、大きく分けて2つの種類に分けられます。
- 写真撮影のために作られたフォトスタジオで撮影する「スタジオ撮影」
- 屋外や結婚式場で撮影する「ロケーション撮影」
スタジオ撮影

スタジオ撮影は、様々な背景シーンの中で写真を撮るプランです。
天候や人流に左右されず、どのタイミングでも素敵な撮影ができるのが魅力。
お気に入りのセットがあるフォトスタジオや、人気のカメラマンがいるフォトスタジオなどから選ぶことが多いようです。
ロケーション撮影

ロケーション撮影は、公園や式場のガーデンなどであればペットと一緒に撮影できるところも多くとても人気です。
結婚式場館内では、チャペルや披露宴会場など様々なフォトスポットで動きのある写真撮影が撮影でき事が最大の魅力です。
「新婚旅行も兼ねてのフォトウェディング」「憧れのリゾート地でフォトウェディング」など、プラスαの魅力があるのもメリットです。
フォトウェディングと結婚式を比べてみると、準備期間が短くても撮影できる、結婚式と同じように衣装選びができる、結婚式より費用を抑えることができる、ゲストの予定を合わせなくて良いので好きな時期に撮影できるなどたくさんのメリットがあります。

日本国内だけでなく、海外でフォトウェディングを行う方も。
初めて旅行に行った思い出の地、テレビや雑誌でよく見るフォトジェニックスポット、幸せになれると言われている場所、撮影が許可されている場所であれば基本的にフォトウェディングを行えます。
フォトウェディングが気になる方は、ぜひこちらも参考にしてください。
フォト+会食の配慮するポイントとは?
一般的な結婚式に比べて、フォトウェディング+会食のスタイルは準備期間が短く、新郎新婦の準備の負担が軽減されるのが魅力のひとつです。
ですが、ゲストにも日程調整などの準備は必要になるので、大まかな開催日程が決まったら早めに報告しましょう。

また家族だけで行うのか、友人まで呼ぶのかどうかまで事前に検討しておく必要があります。
結婚式に参加されるゲストの割合で、家族や親族が多く友人が数名参加する場合は、ご家族とご友人の関係性によっては友人の方が気を遣われることもございます。
参加してほしい友人には、事前に家族メインの結婚式であることをしっかり伝え、出席の意志があるかどうかを伺っておき、気を遣わせないよう考慮した席決めが必要です。
また、フォトウエディングはおふたりのみで行うのか、家族や友人にも参加してもらうのか事前に決めておきます。
おふたりがフォトウェディングを行っている間の撮影に参加しない家族の待機場所や、どのタイミングで参加してもらうかなども確認をしておきましょう。
フォトウエディングを行う撮影場所と会食会場がそれぞれ離れている場合は、移動時間もかかります。
ゲストの移動手段などを考慮し事前に告知しておくことで、結婚式当日はスムーズな1日となるでしょう。
会食(食事会)におすすめの場所は?
フォトウェディングを行ったあとの会食会場はどこになるのでしょうか。
フォトウェディングを結婚式場内で行った場合、そのまま結婚式場の披露宴会場、会食会場を利用することができます。

土日祝日は多くの結婚式を行っているため、平日限定や直近限定として打ち出している会場が多くなります。
また大安や友引などのお日柄が良い土日祝日には、フォトウェディングを承っていない会場がほとんどになりますので、結婚式場でフォトウェディングを行う場合はご注意が必要になります。
平日参加が難しいゲストがいれば、新郎新婦だけ平日にフォトウェディングを済ませ、土日祝日に会食をするという方法を選ばれると良いでしょう。
もちろん、撮影した会場以外のレストランや料亭で会食をされても問題ございません。

スタジオや屋外でのロケーションフォトを選択される場合は、お食事ができる会場が併設されていませんので、会食会場を別に予約する必要があります。
会食におすすめの場所としては、撮影場所や駅に近いアクセスが良いレストランや料亭、個室になっていて婚礼衣装でお過ごしいただける場所です。
個室がある会場であれば婚礼衣装を着ていても周りの目を気にせずにお食事をお楽しみいただけます。
フォトウェディング+会食(食事会)それぞれの衣装はどうする?
フォトウェディングは、和装でも洋装でも、和洋装でも撮影ができます。
衣装ごとに撮影プランが用意されていますので、着たい衣装を着てお写真を残せます。

それでは、会食時の衣装はどうでしょうか。
こちらも、和装でも洋装でも問題ございません。
フォトウェディングでは、和装で撮影後ドレスとタキシードに着替えて食事をする方もいれば、会食会場が和の雰囲気の料亭だから、和装を着て食事をするという方もいます。
会食会場に制限がなければ、お好みの衣装を着てご参加できます。
また、必ずしも婚礼衣装でなければならないということはございません。
よりアットホームでいつもの雰囲気で楽しみたい方は、平服に着替えて参加すると良いです。
その際は、ゲストが浮いてしまわないように事前に服装の指定をしておきましょう。
フォトウェディング時のドレスの選び方について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
フォト+会食(食事会)のプラン内容とは?

撮影と会食を1日で完結することができる、フォトウェディングと会食会がセットになっているお得なプランを出している式場は多くあります。
プランの中身は、どのような内容となっているのでしょうか?
- 新郎新婦の婚礼衣装×1着ずつ…着数を増やしたい方は、2着プランにするかオプション料が発生します
- 新郎新婦の着付け、ヘアメイク…プロによる着付けとヘアメイクが入ります
- 介添え料…婚礼衣装を着た花嫁のサポートをします
- 撮影料…プロのカメラマンによる撮影
- 撮影データ、写真…データ納品が入っているプラン、写真のみ納品でデータはオプションとなるプランがあるので確認が必要です
- 食事会場費…食事会を行うレストラン、料亭の室料
- 食事代…プラン適用人数が決まっているので、人数が増えたり、お料理のグレードを上げると追加料金が発生します
このような内容がベーシックなプラン内容となることが多いです。
洋装や和装、どちらも着たい場合、撮影場所が1か所ではなく室内とロケーションの両方行う場合などは希望条件にマッチしたプランを選ばれるとお得です。
司会者やムービー演出、テーブル装花、ウェディングケーキなどが必要な方は、オプションで追加していきます。
フォトウェディングと会食(食事会)の流れは?
フォト婚と会食(食事会)の準備は、通常の結婚式と比べて打ち合わせも少なく準備がとても短いので、忙しくて時間がない方やマタニティの方にもおすすめです。
フォトウェディングと会食をセットで行う場合は以下のような流れで行います。
- 会場の下見と選定
- 会場スタッフとの打ち合わせ
- 招待客へ招待状の送付
- 衣装の選定
- (希望があれば)席次表/ウェルカムボードの作成
それでは詳しく見ていきます。
会場の下見と選定
まずは、フォトウェディングと会食が行える場所を探します。
Wedding tableでは、フォトウェディング+会食を行っている会場をご紹介しています。
撮影と会食だけでも一度、見学に行かれることをおすすめします。
ホームページを見て気になっていた場所が、実際に話を聞いてみるとオプションで追加しなければ撮れない場所であったという失敗を防げます。
会食会場の雰囲気やスタッフさんの対応も気になるところですね。
会場の下見に関して、注意点やポイントをまとめた記事がございますので、気になる方はぜひご覧ください。
会場スタッフとの打ち合わせ
日程調整や当日の流れなどをプランナーと確認後、申込みをします。
申し込み後、数回プランナーさんと打ち合わせをするのが通例ですが、フォトウェディングの場合は通常の結婚式よりも少ない回数で終えることが多いです。
打ち合わせ回数について気になる方は以下の記事をご覧ください。
招待客へ招待状の送付
会食日程が決まったら、招待する家族や親族へ招待状を出します。
家族のみで行う場合は招待状を出さないこともあるので、その場合は準備の手間が省けますね。
招待状を送る際はゲストの都合もありますので、3ヶ月前までに送るのがベストです。
また、その際の文章やポイントも気をつけたいところ。詳しくは以下の記事をご覧ください。
衣装の選定
無事に会場が決まったあとは、新郎新婦が着る婚礼衣装のセレクトを行います。
一生に一度の結婚式、お気に入りのドレスを選びたいですよね。
Wedding tableでは専門のウェディングドレスプランナーが多数在籍しているため、あなたにお気に入りの一着がきっと見つかります。
ウェディングドレスの選定に不安な方は一度プロに相談してみても良いでしょう。
(希望があれば)席次表/ウェルカムボードの作成
人数変更や食事メニューの変更など特別な対応がなければ、準備はこれだけで整います。
少人数の会食であれば、席次表や席札は無くても良いですが、より和やかな会にするにはウェルカムボードや席次表、席札などを作っても良いでしょう。
少人数の食事会を行う際の席次表、席札の準備については、こちらの記事をご覧ください。
親孝行できる!フォト+会食(食事会)のすすめ
フォトウェディングで撮ったお写真は、お二人の手元に残りますがゲストは見ることができません。
ご両親は、お二人の晴れ姿を見たいものです。撮影データを追加して、台紙やアルバムに入れてご両親へ届けてみてはいかがですか。
きっと、手元に届いたお写真を見てご両親は喜んでくれると思います。
お写真1枚でも、ご両親にこれまでの感謝とお二人のこれからの幸せが伝わることでしょう。

挙式をされない場合、会食時にセレモニー要素を少し取り入れると結婚に対するけじめや決意をご両親に伝えることができます。
二人でどのような家庭を築きたいか、これまで支えてくれた方への感謝の言葉を述べてみてはいかがでしょうか。
また、指輪の交換やケーキカットを取り入れると、シンプルだけど結婚式らしい雰囲気で行えるのでおすすめです。
【Wedding tableより一言】
大人数の結婚式に苦手意識を持っている人が増えてきているという話もよく伺います。
ご家族そろって食事を囲み、会話をすることは人生であと何回あるでしょうか。
結婚という人生の節目で、今まで育ててくれた両親、親族に感謝の気持ちを伝えてみませんか?
ご紹介したフォトウェディング+会食スタイルは、派手ではないけれど感謝を伝えたいという方におすすめのスタイルです。
Wedding tableは、お客様の希望に沿った結婚式スタイルをご提案いたします。ぜひ一度ご相談ください。
この記事を書いた人
- 辻原
- Wedding 婚礼衣装スタイリストとして、約1,000組の新郎新婦を担当してきただけでなく、ドレスショップ勤務の経験も活かし、結婚式準備~結婚式当日までの流れを熟知しているプロフェッショナル。衣装に限らず結婚式のあらゆるジャンルの記事を執筆。保有資格:マタニティの医療サポート認定資格「マタニティコンシェルジュ」



















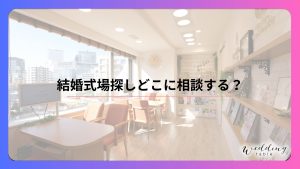




![[準備に時間をかけられなくても大丈夫]これを押さえればOK。2か月前からでも間に合う少人数結婚式で感謝をカタチに](https://www.weddingtable.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/AdobeStock_27770645-970x647-140x140.jpeg)





















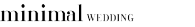







 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)











