婚姻届の出し方完全ガイド/失敗しない準備方法・流れを徹底解説
はじめての方へ | 公開: / 更新:

「婚姻届に印鑑って必要?証人はどうしたらいい?」
「婚姻届の証人は誰でもいいの?」
「そもそも初めてのことなので、どうやって書いたら分からない」
このようなお悩みはありませんか?
法律面でも「正式な夫婦」として認められるには、婚姻届を受理してもらう必要があります。記入方法を間違えたり不備があると、受理してもらえない可能性があります。
もし婚姻届を入籍希望日に受理してもらえなければ、別の日が結婚記念日になってしまいます。こうした事態は避けたいですよね。
当記事では、婚姻届の出し方で失敗しないよう、準備や流れを徹底解説します。
これから提出をする人は、ぜひ参考にしてください。
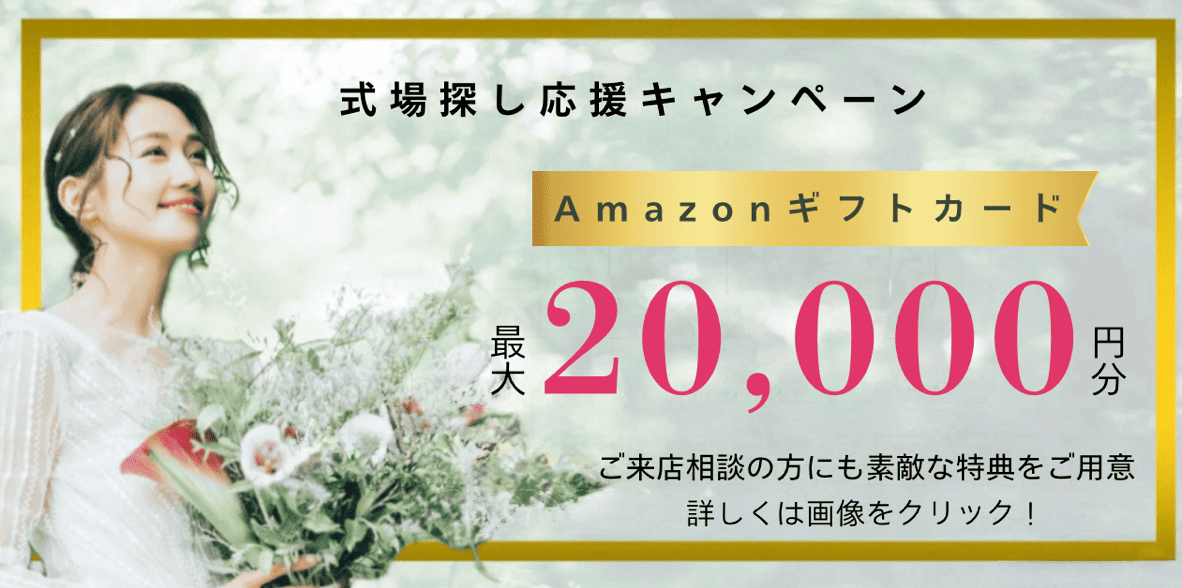
婚姻届を提出する流れとは?

婚姻届を提出する流れはどのようになるのでしょうか?
婚姻届は基本的に提出した日が受理日として、正式に決定されます。
しかし、内容に不備などがあった場合、受理されず結婚記念日がズレてしまう可能性があるため、注意が必要です。
そのような事態を避けるためにも、しっかり流れを確認しておきましょう。
一般的な流れは以下の通りです。
Step0:両親に結婚の承諾を得る
婚姻届を提出する前に重要なことが、お互いの両親に結婚の承諾を得ることです。これはおふたりの状況にもよりますが、一般的にはお互いの両親に結婚の承諾を得てから、婚姻届を提出します。
結婚の事後報告は後に軋轢を生む可能性もありますので、特別な事情がない限りは事前にお互いの両親に挨拶し、承諾を得るようにしましょう。
結婚の挨拶に関しては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
Step1:婚姻届の提出日を決める
両親に結婚の承諾を得たら、婚姻届の提出日を決めます。
提出日は、「ふたりの記念日」や「覚えやすい日」にするケースが多いようです。
婚姻届が受理された日から、法律的に結婚が認められます。
役所によっては、事前に確認してくれるところもありますので、心配の場合は一度相談してみてはいかがでしょうか。
Step2:婚姻届の提出時に必要なモノ・書類をそろえる
役所に婚姻届だけを持参しても、受け付けてもらえません。
なぜなら、ほかにも必要なモノや書類があるからです。
~最低限において必要なモノ~
★婚姻届(書き損じにそなえ、2枚用意すると安心です)
★提出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
ほかにも、どちらかの本籍地以外の役所では、ふたりの戸籍謄本も必要です。戸籍謄本の用意について、場合によっては手元に届くのに2週間ほどかかります。
〜戸籍謄本が必要な場合〜
婚姻届を記載する際に以下の本籍に関連する記載をする必要があります。
・戸籍の筆頭者
・本籍地の住所
・(再婚の場合)離婚した日付
以上の情報が分からない場合、戸籍謄本を取得し、確認することになります。
本籍地と現住所が同じ場合は役所に行って取得することが可能ですが、本籍地が現住所と異なる場合には注意が必要です。
本籍地と現住所が異なる場合の戸籍謄本の取得方法
-
①マイナンバーカードを持っていて、本籍地の自治体がコンビニ対応している場合
→コンビニで(コピー機などで)取得可能。 -
②マイナンバーカードを持っていない、もしくは本籍地の自治体がコンビニ対応していない場合
→郵送で取得可能 - ③本籍地の自治体まで行き、窓口で取得。
以上3つの取得方法があります。いずれにしても取得には一定の手間と時間がかかりますので、それを踏まえて段取りしておきましょう。
また、未成年の結婚では「父母の同意書」が必要であり、外国人との結婚では、日本人の戸籍謄本や外国人のパスポートを求められます。
Step3:婚姻届を用意する
婚姻届を用意する方法は、主に以下の3パターンです。
1、役所の窓口でもらう
2、インターネット上からのダウンロード(A3用紙に印刷)
3、本の付録を使用
上記2、3の場合、様式が合っていれば「オリジナルデザイン」の婚姻届も使用可能です。
ただし自治体によっては、機械で読み込めないといった理由から「オリジナルデザインの婚姻届NG」のケースがあるため、事前確認をオススメします。
Step4:婚姻届に記載する証人を決める
ふたりの結婚を証明するために、2名の証人が必要です。
証人を決めたら、「婚姻届の証人欄」に記入を依頼しましょう。
(※証人になんらかの責任がふりかかることは、一切ありません)
証人は誰に依頼しても構わないものの、「20歳以上」かつ「ふたりの結婚を知る人」という決まりがあります。
一般的には、親やきょうだいに依頼する人が多いでしょう。
また証人2名が、「両者ともに新郎の知り合い」や「知人夫妻」でも構いません。
Step5:婚姻届に必要事項を記入する
婚姻届には、以下の必要事項を記入します。
- 届出日、届け先
・届出日=入籍希望日
・届け先(例:横浜市長) -
氏名、生年月日
名字は結婚前の内容を記載 -
住所
転居届と同時に婚姻届を提出する際には、自治体ごとに「新住所」「旧住所」のどちらを記載するかが異なる -
本籍
不明な場合には、戸籍謄本を見ながら記載 -
婚姻後の夫婦の姓、新本籍
・新本籍は、日本国内の土地台帳に掲載されている住所であればどこでもOK
(例:実家、ディズニーランド、思い出の地)
※遠方だと戸籍謄本を取りに行きにくいので、近場を設定するのがオススメ
婚姻届に「記載モレ」や「誤り」があると受理してもらえないため、記載したあとに間違いがないかを確認しましょう。
Step6:婚姻届を提出する
基本的には、希望日にふたりで婚姻届を提出します。
どちらか1人が届けたり、代理人にお願いすることも可能です。
遠方の場合には、郵送してもよいでしょう。
また婚姻届は、365日24時間いつでも受け取ってもらえます。
しかし役所の営業時間外だと、宿直者に預かってもらうため、ミスがあってもその場で指摘してもらえないケースがほとんどです。
ミスが発覚した場合には、後日修正の連絡がある場合があります。(役所によって対応は様々)
さらに詳しく結婚の手続きについて知りたい方は以下の記事をご覧ください。
婚姻届はどこで出せる?

婚姻届は、ふたりのいずれかの「本籍地」または「所在地」が存在する、市役所・区役所・町村役場で提出できます。
とはいえ、日本国内のどこの役所でも受け取ってもらえます。
(例:結婚式を挙げた先、旅行先、思い出の地)
一時的に滞在している場所であれば可能となっています。
本籍地または所在地以外の役所で婚姻届を提出する際には、ふたりの戸籍謄本を持参しなければいけません。
また事前に、提出を希望する役所に「持参物」を確認しておくと安心です。
2021年9月から印鑑は任意になった

以前は、婚姻届に印鑑での捺印を必要とし、書類の訂正時にも「訂正印」として印鑑が必要でした。
しかし、印鑑は2021年9月から任意になったため、法律的な意味では使用しなくて問題ありません。訂正印も同様です。
ただし、婚姻届に捺印欄は残されているので、記念に押したい場合には使っても構いません(※ただし、インク浸透済のハンコは使用NGです。)
婚姻届の提出で知るべきポイント・注意点

ここでは、婚姻届の提出時に押さえるべきポイント・注意点を紹介します。
コピーは基本的にもらえない
婚姻届の提出時に、コピーは基本的にもらえません。
記念として手元にコピーを残したい場合には、役所の窓口に提出する前に、あらかじめコピーを取っておきましょう。
あとで見返し思い出に浸れるので、オススメです。
また提出時に婚姻届けを手にもち、写真撮影するケースも見受けられます。
意外と多い書類の不備
書類の不備が発覚し、当日中に対応できない場合には、後日婚姻届を提出することになります。
すると、提出日が当初予定した日ではなくなるため、結婚記念日が希望日ではなくなってしまいます。
また記載ミスが発覚した場合には、該当箇所を二重線で引いて訂正するため、婚姻届がキレイではなくなるでしょう。
こうしたケースを防ぐために、婚姻届の提出日前に役所まで出向き、婚姻届の内容チェックをお願いするのもオススメです。
提出したい役所への事前確認は必須
婚姻届を希望日に受理してもらうには、提出したい役所への事前確認が必須です。
当日に不備が発覚すると焦りますし、場合によっては当日中に対応できない内容も存在するからです。
事前確認では、以下をチェックするとよいでしょう。
- 必要な持ち物
- 職員に対応してもらえる受付時間
- ダウンロードや本で入手した婚姻届の受付可否(※該当者のみ)
未成年や外国人との結婚、代理人に依頼するケースでは、ほかに注意する点がないかもあわせて確認しましょう。
まとめ:事前準備で婚姻届け提出をスムーズに

希望日に婚姻届を受理してもらうには、事前準備が必須です。
また夫婦としてのスタートに、結婚式はかかせません。
結婚式は、婚姻届の提出と同日に行うケースもあれば、前後の日程で開催するケースもあります。
同日に実施する場合には、婚姻届を提出する時間や、結婚式を開催する時間も気になりますよね。
Wedding tableでは、婚姻届に関するご相談ごとから、結婚式の手配までトータルサポートいたします。満足いく結婚式を行いたい場合には、Wedinng tableまでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
- Wedding table事務局
- ウェディングテーブルは、あなたにぴったりの会場をご提案する結婚式場紹介サービスです。1000組以上の結婚式をお手伝いさせて頂いた経験を元に、結婚に関するノウハウや知識を発信するコラムを掲載しています。結婚式を挙げようか迷っている方や結婚式に関するお悩みがある方などお気軽にご相談ください。











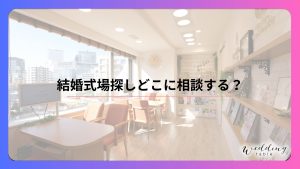


























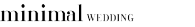







 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)











