略式結納が主流に!正式結納との違い・マナーや関東関西の注意点など
はじめての方へ | 公開: / 更新:

結婚式までに行なう結納は「記念すべきイベント」であり、思い出に残る人も多いでしょう。
これから結納を予定しているおふたりは、自分達はもちろんのこと、参加者全員で気持ちよく行ないたいものですよね。
また昨今の結納スタイルは、正式結納ではなく「略式結納」が主流です。
略式結納とは、どういったものなのでしょうか?
今回は略式結納の基本的な流れやマナー、関東や関西といった地域別の注意点について紹介します。
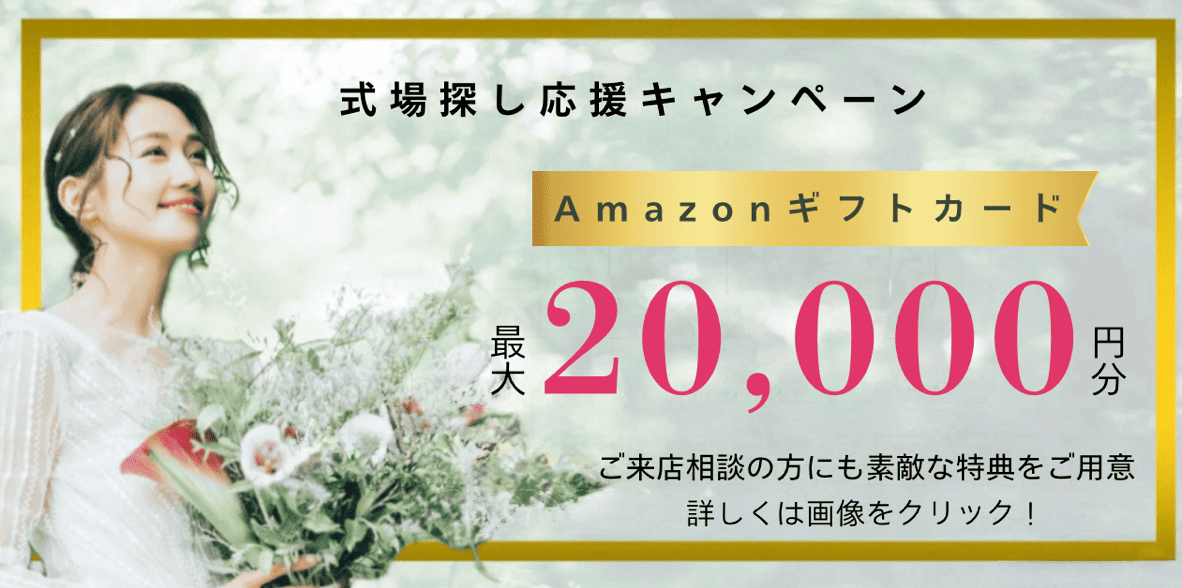
略式結納とは?メリットや正式結納・食事会との違い

そもそも結納とは、婚約を両家の間で確認し、成立させるための日本の伝統的な儀式のことです。
結納は二人の婚約を確認するだけではなく、二人の婚姻によって両家が新たに結びつくことを祝う儀式として両家にとっても大切な意味のある儀式で、結ばれる家と家が、お祝いの品を交換することを意味しています。
結納には「正式結納」と「略式結納」があります。
略式結納とは?正式結納や食事会とどう違う?
略式結納とは、両家がホテル・料亭・女性宅などに集まり、結納品の受け渡しをする結納の儀式を行うことです。
仲人を「たてる場合」と「たてない場合」があるものの、略式結納で仲人が両家を行き来することはありません。
仲人あり・なしの違いは、会の進行役や結納品の受け渡しを、誰が行うのかというところで、「仲人あり」の場合は仲人が行い、「仲人なし」の場合は男性の父親が行うというケースが多いです。
一方正式結納は仲人をたてるのが必須であり、仲人が男性側から結納品や結納金を預かり女性側に渡します。
女性側は仲人をもてなし、男性側に「受書」や「お返しの品」を渡してもらいます。「受書」とは、「結納品をたしかに受け取りました」という証となる書類です。
正式結納は「仲人が両家を行き来して、両家は直接顔を合わせない」、略式結納は「両家が一堂に会して結納の儀式を行う」という大きな違いがあります。
ですが、昨今では、結納は「略式結納」を指すのが一般的です。また顔合わせとも言われる食事会との違いは、結納品や結納金の有無です。両家の親睦を深める目的で結納品や結納金を用意せず、両家が楽しく一緒に食事を行ないます。
略式結納を行なうメリット
上記の通り、昨今では「略式結納」が一般的です。さらに「略式結納」も行わず、「顔合わせ」のみを行なうパターンも増えてきています。
略式結納と顔合わせの違いに関してもしっかり認識しておく必要があります。詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
そんな中、「略式結納」を行うメリットは、どのようなものでしょうか。以下の2点をご紹介いたします。
- 家族が儀礼を重視する場合に、安心してもらえる
- 結婚への自覚が芽生えやすい
家族が儀礼を重視する場合に、安心してもらえる
両家もしくはどちらかの家が「儀礼的な行事」を重視し、結納も重要と考える場合には、略式結納を行なうことで安心してもらえます。
地域によっては「結納は常識」と考えていたり、結婚の段階を踏むために「結納をしてほしい」と願う家族もいるでしょう。
こうした要望にこたえることで、双方の関係性を良好に保てます。
結婚への自覚が芽生えやすい
結納は結婚にまつわるイベントの1つです。
そのため、結納というイベントをふたりが中心に行なうことで「結婚の自覚」を感じやすくなります。同時に結婚への責任も芽生えるでしょう。
結婚への自覚は、お互いを思いやる気持ちにつながり、さらには両家に対する思いやりの増長にもつながります。
略式結納の基本的な流れ

略式結納は、ホテル・料亭・女性側の自宅などに集まって行なわれます。
結納にかかる時間は20分ほどです。
ホテルや料亭などで実施する場合には、個室予約が望ましいでしょう。
略式結納の基本的な流れは以下の通りです。
1、結納品を飾る
まずは、結納がはじまる前に「結納品」を飾りつけます。
男性から飾りつけ、つづいて女性が飾りつける流れが一般的です。
和室の場合には床の間に飾りつけ、床の間がなければ台を用意して毛氈(もうせん)を敷きます。洋室の場合には上座にテーブルを用意し、その上に飾りつけます。
いずれにしても自宅以外の場所で行なう際には、お店のスタッフに事前確認をしましょう。
2、はじまりの挨拶をする
両家が揃ったら「はじまりの挨拶」をします。
男性側の父親が担当するケースが一般的です。父親不在の場合には、母親や男性本人が挨拶を行ないましょう。
仲人を設けるのであれば、仲人が挨拶をします。
3、男性側が結納品をおさめる
略式結納がはじまったら、最初に男性側が結納品をおさめます。
男性の母親が、女性の前に盆ごと結納品を持っていき、一礼して渡します。
結納品には、親やきょうだいの名前や関係性を示した「家族書」をつけるケースも多いです。(親戚情報も記載するケースもあり)
男性の母親が席に戻ったら、男性の父親が一礼します。
4、女性側が受書を渡す
女性本人が目録を確認したら、自身の父親、母親の順に回します。
目録が戻ってきたら、女性本人が一言お礼をしましょう。
その後、女性の母親が結納品を「飾る場所」に運び、受書をもって男性の前に置きます。
一礼をしたら、席に戻ります。
5、結納返しをおさめる
戻ってきた女性の母親は、つづいて「女性側の結納品」を取りに行き、男性の前に置きます。
男性の結納品と同様に、家族書をつけるケースも多いでしょう。
女性の母親は一礼をし、自分の席に戻ります。
6、結婚記念品をお披露目する
婚約指輪などの記念品を用意している場合には、この場で両家にお披露目をしましょう。
記念品のお披露目に、喜ぶ家族は多いものです。
お披露目と同時に、男性から「結納の場を設けてもらったこと」など、感謝の言葉を述べるとよいでしょう。
7、締めの挨拶をする
最後に、男性の父親が締めの挨拶を行ないます。
つづいて、女性側の父親がお礼の言葉を述べるケースが一般的です。
略式結納が終わったら、写真撮影や食事会がはじまります。
略式結納のマナー・注意点

略式結納のマナーや注意点をおさえ、両家が気持ちよく過ごすためには、以下を意識するとよいでしょう。
両家の服装を合わせる
フォーマル・セミフォーマルは問わないものの、両家の「服装の格式」を合わせることは重要です。
また主役のおふたりより、両親や家族の服装が格上にならないよう注意します。
昨今では、男性がスーツで女性がワンピースといった「カジュアルな服装」も増えており、こうしたケースでは両親や家族も同様の格好でよいとされます。
席順に配慮する
席順は、結納品の置き場所を前にし、男性側が左で女性側が右に座るケースが一般的です。
出入り口から遠い上座が本人で、つづいて「父親→母親→きょうだい」といった順に座ります。
結納品は省略してもよい
結納品は、品目数を減らすのはもちろんのこと、省略してもマナー違反にはあたりません。
ただし「割り切れない数(つまり奇数)」で用意しましょう。
なぜなら、割り切れてしまうと縁起が悪いとされるからです。
略式結納_関東と関西の違いとは?どちらに合わせる?

ふたりの出身地が異なり、結納の考え方に差があると「どちらに合わせるか?」と迷うこともあるでしょう。
実際に結納には地域差があり、ざっくりと「関東式」「関西式」にわけられます。
| 関東式 | 北海道、東北地方、関東地方、新潟県、静岡県、沖縄県 |
|---|---|
| 関西式 | 関西地方、東海地方(静岡除く)、北陸地方(新潟除く)、中部地方、中国四国地方、九州地方 |
(※さらに地域差があるものの、ここでは関東式・関西式にわけて説明します。)
違い1:結納品の扱い
関東式は、結納品を男性と女性の双方が贈りあうと考えます。
そのため関東式の地域では、結納を行なうことを「結納を交わす」と表現するのです。
一方関西式は、男性側だけが結納品を送り、女性は受書だけを渡します。
違い2:結納返しの金額
結納返しとは、結納を受け取った側が、相手にお返しを贈ることです。
関東式では、男性側から結納金をもらった場合に、女性側は結納金の半額程度のお金や品物を渡します。
一方関西式は、結納返し自体を実施しないケースも多いです。結納返しをする場合にも、結納金の1割程度にとどまります。
とはいえ、昨今では結納金を準備しないケースもあり、ケースバイケースだと言えるでしょう。
出身地が異なる場合、どちらに合わせるのが正解?
おふたりの出身地が異なる場合には、どちらに合わせるというよりも「結納金を準備するか?」や「結納返しは必要?」などを話し合って決めるのがベストです。
男性側の両親が「女性側に合わせる」という場合には、女性側のスタイルに合わせてもよいでしょう。
まとめ:略式結納が終わったら結婚式の準備へ
無事に結納が終わり、両家の親睦が深められたあとには、いよいよ結婚式の準備です。
略式結納にもそれぞれの形があるように、結婚式にもそれぞれの形があります。
Wedding tableでは、おふたりらしい結婚式ができるよう、専用のコンシェルジュがおふたりにピッタリの方法でサポートいたします。
家族のみのアットホームな結婚式、友人や上司も招く賑やかな結婚式、写真のみのフォトウェディングなど、さまざまなサービスを展開中です。
おふたりの希望に叶う結婚式をご提案いたします。ぜひWedinng tableまでお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
- Wedding table事務局
- ウェディングテーブルは、あなたにぴったりの会場をご提案する結婚式場紹介サービスです。1000組以上の結婚式をお手伝いさせて頂いた経験を元に、結婚に関するノウハウや知識を発信するコラムを掲載しています。結婚式を挙げようか迷っている方や結婚式に関するお悩みがある方などお気軽にご相談ください。










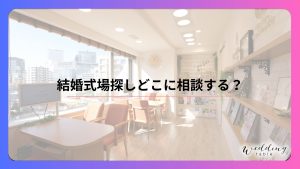


























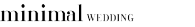







 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)











