結婚式をしない場合のご祝儀って? 親や親族からもらった場合の対応は
豆知識・費用・相場 | 公開: / 更新:

「ご祝儀」と聞くと、結婚式を行った際にゲストからもらうものというイメージがある人も多いのではないでしょうか。
それとは別に、親が「結婚式費用の足しに」という意図でご祝儀を渡すケースも多くあります。
一方、ナシ婚では結婚式を行わないため、親からのご祝儀があるかわからない人もいるでしょう。
また、もしご祝儀をもらったとしてもどのようなお返しをすればいいのかも気になるポイントです。
この記事では、ナシ婚における親からのご祝儀について解説します。
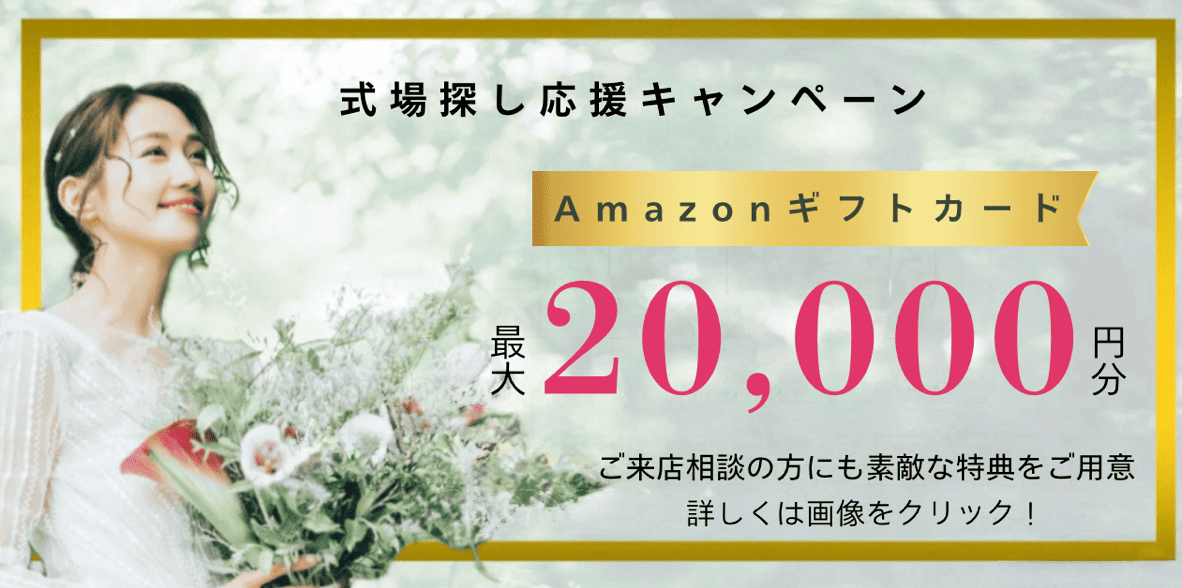
結婚式をしない場合の「親からご祝儀」について
まず、ご祝儀はあくまでも結婚に対するお祝いの気持ちであり、結婚式費用の支払いに充てるためのものではありません。
しかし、結婚式を行う場合は参加費と似た意味合いでご祝儀を持ってくるゲストも多いのが実情です。
そのため、ゲストの属性によってある程度相場が決まっています。
一方、親からのご祝儀は人によって認識が異なります。
また、必ずしも現金である必要もありません。
結婚式の費用を親が支払うことによってご祝儀とする人もいれば、新生活の家具家電を購入することをご祝儀とする見方もあるでしょう。
中には昔ながらの風習にのっとって訪問着やタンスなどを贈るケースもあります。

昨今ではこのような選択をする親は少なくなっており、現金を渡す親の割合が多くなっています。
親が子どもに現金でご祝儀を渡す場合は、10~30万円が多いようです。
親族や友人からのご祝儀は結婚式の有無によって大幅に金額が異なる一方で、親からのご祝儀に関しては大きな違いはありません。
「何をもってご祝儀とするか」についての認識は人によって異なるものの、ナシ婚であっても親からのご祝儀はもらえることが多いと考えていいでしょう。
結婚式をしない場合は親族からのご祝儀は少なくなる
ナシ婚では結婚式を行う場合と比較して、親族や家族からのご祝儀は少なくなる傾向があります。
結婚式では5万円ほどを包んでくる親族も少なくありません。
兄弟姉妹も同程度の金額が相場です。一方、ナシ婚の場合は兄弟姉妹、いとこからは5千~1万円、おじ・おばからは1~3万円程度のご祝儀であることが多いでしょう。
このように、結婚式を行わないことがご祝儀の金額に影響を与えることは否定できません。
そのため、ご祝儀はナシ婚のほうが全体的に少なくなると考えたほうがいいでしょう。
一方、ご祝儀から手元に残る金額を考えた場合、一概に「ナシ婚のほうが少ない」とは言い切れない実情もあります。

一般的な披露宴では、料理や飲み物に2万円、引出物などに1万円ほどかかることが多いため、5万円をもらったとしてもその差額は2万円程度です。
そう考えると、ナシ婚で多く見られるご祝儀の金額も決して少ないわけではないことがわかります。
例外として、ご祝儀を贈る側がすでに結婚式を行っていた場合は、お返しの気持ちも添えてもらったご祝儀と同額を贈ることがあります。
このように、結婚式の有無にかかわらず、相手との関係性やこれまでの経緯も考慮して金額を決める人もいるようです。
特に、親族間ではこの傾向が強いため、結婚式をしない場合はできるだけ早くその旨を伝えるのが好ましいでしょう。
ご祝儀の金額で両家に差があったらどうする?
金銭感覚は人によって異なります。
そのため、親からのご祝儀に両家で差が出ることも少なくありません。
そうはいっても、金額に差があると5割近くの人はもやもやした気持ちになるという調査結果もあり、ネガティブな心境に陥ってしまうこともあります。
ここでは、以下のケースにおける考え方を紹介します。
・相手の親から援助の話がない
そもそもご祝儀は「援助」ではありません。
結婚はあくまでもふたりが一人前の大人として家庭を築くものです。
そのため、まずは援助を受けて当たり前という気持ちを払しょくしましょう。
新生活には何かとお金がかかるため、親からの援助は確かにありがたいものです。
しかし、人の道理として援助を受ければいつか返さなければならないときがやってくることも事実です。
後々まで「援助した」という事実を親が持ち出す可能性もあります。
見返りを求めない援助はないと考えれば、援助の話がなくても気持ちが楽になるでしょう。
・片方の親からだけもらうのは納得がいかない
結婚後にその夫婦に入ってくるお金は、夫婦共有の財産になります。
両方の親からもらおうと、片方の親からだけもらおうと、出所が違うだけでふたりがもらったお金に変わりありません。
確かに「自分の親はご祝儀をくれたけれど相手の親はくれない」というような状況には納得がいかないかもしれません。
しかし、そもそもご祝儀は結婚をお祝いする気持ちを表現する方法であり、両家平等でなければいけないという決まりはないものです。
金額がいくらであってもご祝儀をいただいたことに感謝し、ふたりの財産として有意義な使い方を考えましょう。

・ご祝儀の金額に差がありすぎる
事前に「ご祝儀をいくら渡すか」というすり合わせを行う両家はまずありません。
一方の親は10万円、もう一方の親は100万円ということもあります。
一見すると10万円のほうは祝福の度合いが低く、100万円のほうは心から喜んでくれているように思えるかもしれません。
しかし、家庭にはそれぞれの経済事情がありますし、ご祝儀の金額と子どもへの愛情はまったく別物です。
たとえば、相手の兄弟は3人、自分は1人といった状況で、相手の親から30万円、自分の親から100万円もらったとしても、金額の是非を問うことはできないでしょう。
生まれてからこれまで、親は多くのお金と労力を使って自分を育ててくれたことに変わりありません。
金額を比較するよりも、お祝いの気持ちを素直に受け取ることが大切です。
親からのご祝儀に結婚内祝いはいる?
ご祝儀はお返しを用意するのが基本です。
結婚式を行う場合は、料理や引出物などがお返しとなります。
一方、ナシ婚では料理の振る舞いや引出物を渡すといったことはありません。
そのため、お返しをする際には内祝いの形をとるのが一般的です。
もちろん、親は内祝いを期待してご祝儀を渡すわけではありません。
しかし、結婚は親の元から巣立って一人前になることを意味するため、その証として内祝いを渡すのがおすすめです。
親のご祝儀に対する内祝いは半返しや3分の1返しが多い傾向があります。
そうはいっても、高額なご祝儀に対してはこの基準を重視する必要はありません。
たとえば、100万円のご祝儀に対して50万円の半返しは必ずしも必要ないでしょう。
気持ちが伝わる内祝いであれば親は十分に喜んでくれます。

贈り物としては、同じ時を刻むという意味を込めた時計や使い込むほどに味わいが出る万年筆などの筆記具、夫婦でゆっくりと旅を楽しめる旅行券などがおすすめです。
また、ふたりの名前や結婚した日を刻んだ食器は従来から人気がありますが、極端に目立つ文字入れは避けたほうがいいでしょう。
そのほかにも、親が以前から欲しいと言っていたものを選んだり、少し豪華な食事に招待したりするのもいい方法です。
贈り物には形に残るものと残らないもの、思い出を重視するものと未来に生きるもの、実用性の高いものと装飾品として価値があるものなどがあります。
選び方に正解はなく、どれが喜んでもらえるかもその親によって異なるのが実情です。
普段の親の言動を思い出しながら感謝の気持ちを込めて選びましょう。

一方「親からご祝儀をもらったら内祝いでお返しをすればOK」という考えは早計です。
たとえ内祝いをしっかりと贈ったとしても、その後の生活で援助を懇願したり親に依存した過ごし方をしたりするのでは、結婚を祝福してくれた親の気持ちを台無しにすることになります。
内祝いという形にこだわる以上に、自立した大人として新たな家庭を堅実に築いていくことが、親に対する何よりのお返しになることを忘れないようにしましょう。
親でも親族でもご祝儀をもらったら感謝の気持ちを伝えよう
結婚式をしない場合のご祝儀は参加費としての意味を持たない純粋なお祝いの気持ちです。
用意してくれるだけでも本当にありがたいことだと考えましょう。
親族はもちろん、親に対しても内祝いを贈ることで、ご祝儀をもらったことに対する感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。
親にも親族にも「ご祝儀を贈ってよかった」と思ってもらえるような対応を心がけましょう。
この記事を書いた人
- Wedding table事務局
- ウェディングテーブルは、あなたにぴったりの会場をご提案する結婚式場紹介サービスです。1000組以上の結婚式をお手伝いさせて頂いた経験を元に、結婚に関するノウハウや知識を発信するコラムを掲載しています。結婚式を挙げようか迷っている方や結婚式に関するお悩みがある方などお気軽にご相談ください。









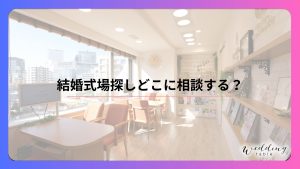


























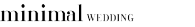







 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)











