結婚式をしないカップルにご祝儀を渡したい! いつ渡すのがベスト?
豆知識・費用・相場 | 公開: / 更新:

近年は、結婚式をしない選択をするカップルも少なくありません。
周囲にも結婚はするけれど結婚式はしないカップルがいる人も多いのではないでしょうか。
そこで気になるのがご祝儀を渡すタイミングです。
結婚式があればそのときに持参すれば問題ないのですが、結婚式がない場合はどうすればいいのでしょうか。
この記事では、結婚式をしない友人や知人に対するご祝儀について解説します。
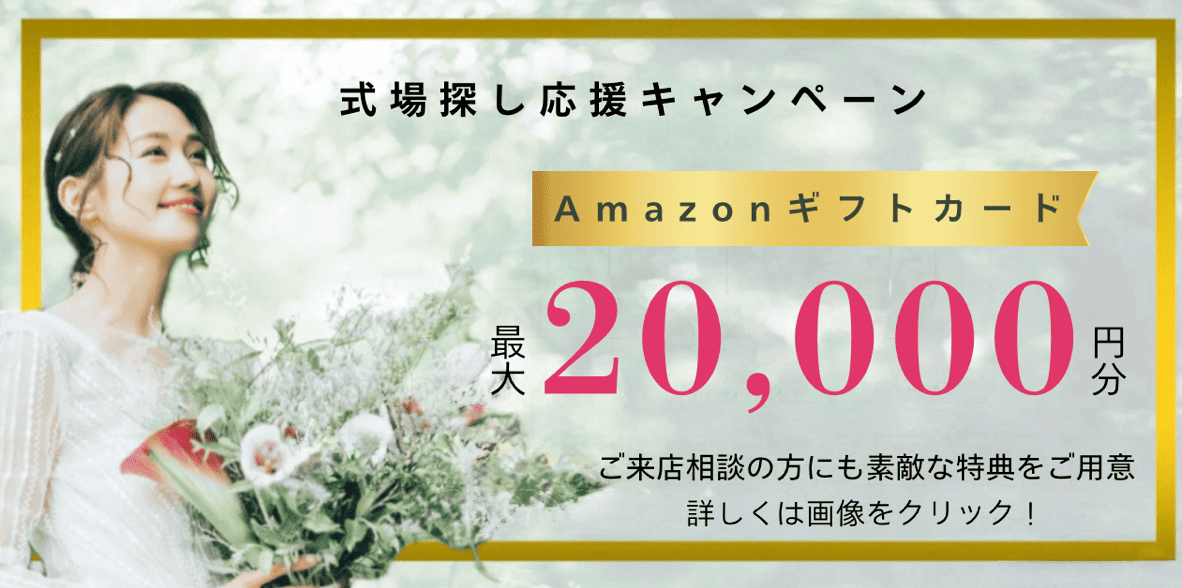
ご祝儀はいつ渡す? 基本のマナーとタイミングとは
ご祝儀は必ずしも「結婚式で渡すもの」というわけではありません。
結婚式の有無にかかわらず、ご祝儀には基本的な考え方があります。
まず、ご祝儀を渡す時期は結婚報告を受けた後1ヶ月以内だと考えましょう。
直接渡すのが基本ですが、遠方に住んでいたり、都合が合わなかったりする場合は配送でも問題ありません。
贈るものは大きくギフトと現金に分けられます。
配送でギフトを贈る場合は宅配便などを利用して問題ありません。
一方、郵便で現金を送る方法は現金書留に限られます。
普通郵便では送れないので注意しましょう。

また、相手の自宅以外の場所でギフトを手渡しする場合は、重さにも配慮が必要です。
重量のあるギフトは持ち帰りに不都合が生じるため、できる限り配送しましょう。
これらの基本的な考え方からすると、結婚式を行う場合のご祝儀はむしろ例外とも捉えられます。
結婚式で受付に渡すご祝儀は、結婚式への参加費という意味合いが強くなっているのが実情です。
結婚報告を受けたとしても、同時に結婚式の実施について案内がある場合は、結婚式にご祝儀を持っていく必要があります。
そのため、1ヶ月という期限にこだわる必要はありません。

また、現金ではなくギフトを渡すという選択肢もなくなるでしょう。
本来、結婚祝いはふたりが新生活に必要なものを贈るものですが、結婚式にギフトのみを持っていくというのは非常に稀なケースです。
渡し方も直接渡したり配送したりするのではなく、受付を担当する人に渡すのが一般的になっています。
一方、ご祝儀としての現金に加えてギフトも渡すのはまったく問題ありません。
しかし、結婚式当日は新郎新婦との時間を十分に確保することは難しいため、あらかじめ渡せる日時を確認しておきましょう。
渡す日に関しては縁起がよいといわれる大安や友引の日がベターとされています。
しかし、結婚式を行う場合、その日が必ずしも大安や友引に該当するとは限りません。
また、午前中は縁起がよいとされる先勝や午後は縁起がよいとされる先負、正午前後が縁起がよいとされる赤口などは、その時間に会ったり配送時刻を指定したりするのが難しいケースもあります。
そのため、極度に縁起がいい日にこだわる必要はありません。
それよりもこちらの都合を優先してほしいと考えるカップルも多いでしょう。
六曜にこだわるか否かは信仰する宗教によっても異なりますし、日にちに優劣をつけるのはナンセンスという考えを持つ人もいます。
ご祝儀を贈るにあたっては、さまざまなマナーがありますが、それらがすべて相手にとってベストであるとは限りません。
「この人はテキパキと行動する人だ」
「家に物を増やしたくない人だ」
「合理性を求める人だ」といったように、
相手の事情や考え方を考慮して検討することが大切です。
結婚式をしないカップルへご祝儀を渡すタイミングは?
相手が結婚報告と同時に結婚式をしないという意志を伝えてきた場合は、その報告が婚姻届を提出する前か後かによって、ご祝儀を渡すベストなタイミングが異なります。
「結婚する予定」という段階での結婚報告であれば、婚姻届を提出する日から逆算して一週間前を目途に贈りましょう。
既に結婚している段階での報告や、明日にでも婚姻届を提出するという状況なら、報告を受けてから1ヶ月以内で問題ありません。
そうはいっても、結婚報告を受けたらすぐに行動するのがベターです。
なるべく早めに贈ったほうが相手の心証もよくなるでしょう。
その間に相手と会う機会があるのなら、直接渡すのがベストです。
会うことでお祝いの言葉も直接伝えられますし、相手も結婚式がない中で会えたことをうれしいと感じてくれるでしょう。

しかし、贈るギフトが重い、1ヶ月以内に相手と会う機会がないといった状況では配送したほうがいい場合もあります。
配送する場合は、手紙や手書きのカードを同封するなど、ひと手間かけるだけで祝福の気持ちも伝わりやすくなるでしょう。
ご祝儀は直接渡せないことよりも、渡す時期が遅れることのほうが問題です。
タイミングが合わないからという理由で会う日を引き延ばすよりも、時期を逃さないよう手配することが大切です。
授かり婚(マタニティウエディング)で結婚式をしない場合のご祝儀はいつ渡す?
授かり婚でのご祝儀は少し事情が異なります。
結婚祝いとしてのご祝儀に加えて出産祝いについても検討する必要があるためです。
結婚報告を受けたとき、相手がすでに出産している場合は結婚祝いと出産祝いを同時に贈って問題ありません。
しかし「このギフト一点で結婚祝いと出産祝いを兼ねる」とするのは考え物です。
そもそも結婚祝いと出産祝いは贈る目的が異なります。
結婚したふたりに対して贈るものと、出産したふたりに対して贈るものとでは内容が変わるのが当然であり、相手もそう認識している可能性が高いでしょう。
そのため、ギフトを贈る場合は結婚祝いと出産祝いで別のものを用意する、両方とも現金で贈る場合は金額を考慮することが必要です。
一般的なご祝儀の相場とされる金額を「出産祝いも兼ねたご祝儀」とするのは避けましょう。
渡すのは同時であっても、封筒を分けて贈るとより本来の意味に沿った贈り方になります。

一方、結婚する予定の段階での報告や、結婚はしたが出産はまだというケースの結婚祝いと出産祝いは、時期をずらして贈るのがベターです。
あくまでも出産祝いは、子どもの誕生に対して贈るものであり、予測に基づいて贈るのは好ましくありません。
妊娠や出産では何があるかわからないのが実情です。
その段階での出産祝いは時期尚早と捉えられる可能性もあります。
まずは結婚祝いを贈り、その後に出産の報告を受けてから出産祝いを贈りましょう。
再婚で結婚式をしないカップルのご祝儀はいつ渡す?
近年は再婚するカップルも増えてきています。
友人や知人が再婚するとなった場合、ご祝儀をどうすればいいか迷う人もいるでしょう。
再婚であっても、一般的なマナーに沿ってご祝儀を渡して問題ありません。
一方、付き合いの長い友人などの場合は、初婚時にもご祝儀を贈っているケースも多いでしょう。
贈る側が祝福の気持ちをもって初婚時と同様にご祝儀を贈りたいと考えても
「またご祝儀をもらうのは申し訳ない」
という気持ちから、相手が遠慮してしまうこともあります。
そのため、初婚時以上の金額の現金や高額なギフトを贈ることを避ける人が多いのも実情です。

このような状況では、贈る側の気持ちよりも贈られる側の気持ちを優先するほうがベターです。
相手の気持ちや状況に配慮したご祝儀の贈り方としては、自分の好みで選ぶのではなく相手にほしいものを聞く、個人で贈るのではなくグループで贈るなど、さまざまな方法があります。
再婚で結婚式をしないカップルへのご祝儀は3000~10000円が相場です。
現金の場合はこの相場を参考に金額を決めて問題ありませんが、ギフトの場合は本人の嗜好なども考慮して贈り方を考えましょう。
双方にとって極端に気を遣う必要がない範囲で検討しましょう。
結婚式をしないカップルのご祝儀はいつ渡す? まとめ
ご祝儀を贈ることは、結婚を祝福する気持ちを相手に示す有効な方法です。
もちろん、言葉で「おめでとう」というだけでも気持ちは伝わりますが、ご祝儀があるのとないのとでは相手の心証が大きく異なることは否めません。
結婚式を挙げなくても、祝福の気持ちはご祝儀という形でしっかりと伝えましょう。
ご祝儀は、時期を逃すと「今さら」という印象を与えかねないため、贈るタイミングが重要です。
婚姻届を提出した後の報告であれば1週間前、婚姻後では遅くとも1ヶ月以内がベストなタイミングであると心得て、適切な時期に贈りましょう。
この記事を書いた人
- Wedding table事務局
- ウェディングテーブルは、あなたにぴったりの会場をご提案する結婚式場紹介サービスです。1000組以上の結婚式をお手伝いさせて頂いた経験を元に、結婚に関するノウハウや知識を発信するコラムを掲載しています。結婚式を挙げようか迷っている方や結婚式に関するお悩みがある方などお気軽にご相談ください。









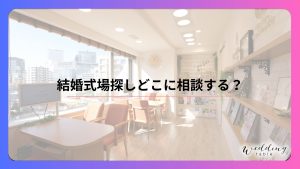


























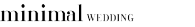







 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)











