家族との結婚式のご祝儀はいくら?相場や渡し方・お返しのマナーを紹介
豆知識・費用・相場 | 公開: / 更新:

親族のみでおこなわれる家族との結婚式では、挙式の費用を抑えられるという点に大きなメリットがあります。
ただ、多くのゲストを招待できる一般的な挙式に比べて、家族との結婚式では招待できるゲストの人数も限定的です。
そのため、通常の挙式ほどのご祝儀は期待できない場合が多いです。
実際の家族との結婚式では、通常いくらくらいのご祝儀が期待できるものなのでしょうか。
ここでは、家族と過ごす結婚式のご祝儀の相場や渡し方やお返しのマナーなどについて解説します。
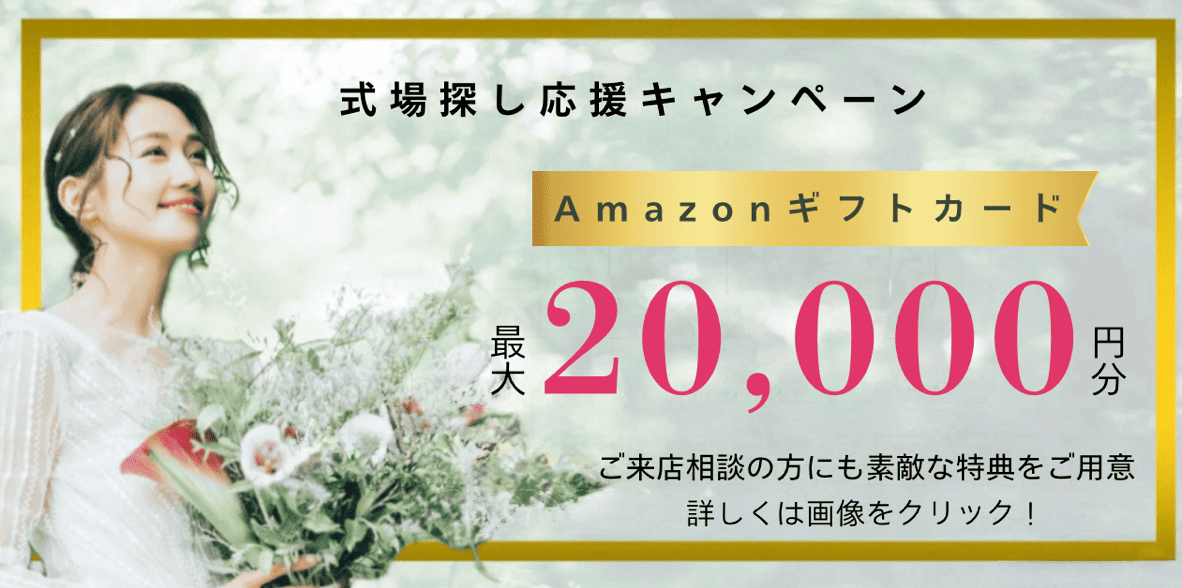
1 家族との結婚式のご祝儀の相場
親族の結婚式に出席する場合、包むべきご祝儀の相場は3~10万円程度といわれています。
もちろん、本人との関係性が深い場合は多めの金額を包む場合もあり、年齢や未婚・既婚などによっても金額の相場は変わってきます。
たとえば、兄弟姉妹の場合は3~5万円程度がご祝儀の相場です。
ただし、兄弟姉妹でも未婚者ならご祝儀の相場も減るのが通常です。
未婚者の場合は3~5万円、既婚者であれば1家族で7~10万円程度が目安となります。
また、兄弟姉妹がまだかなり若いという場合は、そもそもご祝儀を包む必要がないため、10代や20代の未婚の兄弟姉妹がいる場合はご祝儀を当てにしないほうが良いでしょう。
一方、叔父や叔母など、年齢が上の世代の親族は、ご祝儀の相場も少し高めとなります。
叔父や叔母の場合では5~10万円程度が相場となり、祖父母なら5~10万円以上はご祝儀を包むのが一般的です。
その他の従兄弟などの親族は5~8万円程度が相場です。
2 ご祝儀の渡し方

友人や知人の結婚式に参列する場合は、挙式の当日にご祝儀を渡すのが一般的です。
一方、親族の結婚式の場合は、挙式当日ではなく、それより前にしっかり準備をして渡すのがマナーとなります。
ただし、挙式直前は新郎新婦も準備に追われていることが多いため、結婚式より前にご祝儀を渡す際は、挙式の1週間位前を目安に渡すのが望ましいといえるでしょう。
もちろん、ご祝儀を渡す日は大安などなるべく縁起の良い日を選ぶことも大切です。
自身の都合や六曜とも合わせて、最適な日に渡せるように日程を調整しましょう。
ただし、親族が遠方に住んでいるなど、やむを得ない事情で結婚式前にご祝儀を渡せないといったこともあります。
その場合は、式の当日に渡したとしても問題ありません。ご祝儀は新郎新婦に直接会って渡すのが一番です。
遠方だからといって、ご祝儀を送付したりするのは避けたほうが良いでしょう。
ただ、挙式当日は新郎新婦に会う時間が限られていることもあります。
その場合は、新郎新婦の親にご祝儀を預かってもらうと良いでしょう。
3 ご祝儀なしのケースもある
家族との結婚式では事前にご祝儀を渡してしまうのが一般的です。
ただ、遠方からのゲストは事前に渡せないため、当日に用意して持ってくることになります。
その場合、当日の受付でご祝儀を渡す人とそうでない人が出てきてしまうことになります。
そうした状況では、事前にご祝儀を渡していた人は、当日の受付で何も持ってきていないように見られてしまうでしょう。
そのような人に配慮するため、家族との結婚式では当日のご祝儀は不要とすることもあります。
また、家族との結婚式に限らず、そもそも遠方から招待するゲストにはご祝儀を求めないことが一般的です。
遠方からのゲストは、近場の人と比べて移動費や宿泊費にかなりのお金がかかります。
そうした費用を自己負担してもらう代わりに、ご祝儀をなしにするということも結婚式の基本的なマナーのひとつです。
遠方など特段の事情がなければ、ゲスト自身が自分で判断してご祝儀を用意しないということはまずありません。
ただ、家族との結婚式では全体でいくらくらいのご祝儀を見込めるのか見当をつけるのは難しい場合が多いです。
遠方から招待する親族が多いときはご祝儀が少なくなることもあるので、ご祝儀の見込み額にはある程度幅を持たせて想定しておくと良いでしょう。
4 挙式そのものにかかる相場は?

家族との結婚式は挙式の費用をリーズナブルに抑えられる点にメリットがあります。
実際、一般的な家族や親族との結婚式にかかる費用は70~150万円程度が相場となっており、友人や知人を招待しての結婚式よりもかなり費用を抑えることが可能です。
招待するゲストを親族のみに限定できるため、大きな式場を用意する必要がなく、その分だけ費用を抑えることができます。
たとえば、家族との結婚式における会場費は5万円からというのが相場となっています。
そのほかに、挙式代が10万円から、飲食代が1人あたり1万5000円から、衣裳代が10万円から、引き出物が1人あたり3000円からというのが家族との結婚式の一般的な費用相場です。
ただし、家族との結婚式は招待する人数が少ないだけに、ご祝儀の額によってはむしろ割高になってしまうこともあります。
ですから、結婚式をおこなう場合は、しっかりプランを練ったうえで予算を立てることが大切です。
全体的な費用は少なくても、赤字が出てしまえばその後の結婚生活に影響を与えることもないとはいえません。
家族との結婚式には挙式のみのパックプランを用意している式場もあります。
そうしたパックプランの活用も視野に入れながら、費用を節約できるところはしっかり節約するように心がけましょう。
5 ご祝儀内で家族との結婚式をする会場探しのポイント

もともと費用が安い家族や親族だけの少人数結婚式の場合でも、しっかり考えて準備をすればさらに費用を節約することができます。
工夫次第では、ご祝儀内で式を挙げることも十分に可能です。
そのために重要なのが会場探しです。
式場によっては、家族との結婚式という挙式スタイルに合わせたさまざまなプランが用意されています。
その中には、一見すると料金がお得に見えるプランもあるはずです。
しかし、料金だけでプランを選択するのはなるべく避けたほうが良いでしょう。
大切なのはプランの内容と料金のバランスです。
たとえ料金が安くても、そのプランの中に自分のやりたいことが含まれていなかったら、せっかくの結婚式も満足のいくものにできなくなってしまうかもしれません。
あとになってプランを増やせば、その分だけ費用も上乗せされることになるため、結局損をすることになってしまうでしょう。
結婚式のプランを選ぶ際は、自分が式でやりたい内容が含まれているかどうかをまず見ることが大切です。
そのうえで、料金とのバランスをチェックしましょう。
そうすることが、料金と内容がしっかり整った満足のいく家族との結婚式を挙げることにつながります。
6 家族との結婚式に招待できなかった友人からのお祝いのお返しマナーは?
結婚式に参加されていない友人や知人、または会社の方などからお祝いをもらうケースも少なくありません。
そのようなお祝いに対してお返しをすることを「内祝い」といいます。
「内祝い」を贈る時期は、いつでも良いわけではありません。
結婚式が終わってから「1ヶ月以内」には手配するようにしましょう。
遅くなってしまうと印象が悪かったり、いまさら感が出てしまうので、「ありがとう」の気持ちを込め、早めに贈るようにします。
では、内祝いで贈る品はどのようなものがいいのでしょうか。
まず費用については、いただいた品の金額の半額くらいのものが良いとされています。
ただし、お返しする方が、職場の後輩や部下の場合はお祝いと大体同額程度をお返しするのがマナーです。
1万円いただいたら、8,000円~10,000円の間でお返しするといいでしょう。
その他に、職場の方や友人などで、複数の人から連名でお祝いをもらうケースもあるでしょう。
このような場合は、お祝いの金額を人数分で割ってその金額の半額分をそれぞれの方へ個別に贈るのがおすすめです。
マナーをまもるところはしっかり守り、感謝の気持ちを添えてお伝えしましょう。
7 家族との結婚式におすすめなのはウェディングテーブル
招待客が少ない家族との結婚式では、自己負担額も大きくなると思われがちですが、
しっかり準備をして式に臨めば、ゲストのご祝儀で費用をカバーすることも十分にできます。
また、工夫次第ではご祝儀だけで式全体の費用をまかなえてしまうことも珍しくありません。
まずは少人数結婚式に特化した結婚式会場の情報を得ることが重要です。
そもそも、一般的な結婚式場は大人数の式を想定して作られています。
そのため、家族との結婚式のような少人数結婚式向けのプランはあまり用意していないのが現状です。
そこでおすすめなのがウェディングテーブルです。
ウェディングテーブルでは、家族や親族を中心に招く少人数結婚式に特化した情報を多数提供しており、費用をできるかぎり抑えた家族との結婚式情報や、少人数ウェディング向けの提案をすることができます。
家族との結婚式という挙式スタイルは、費用を抑えられるだけでなく、少人数だからこそのこだわりを反映することが可能です。
ゆっくりとおいしい食事を味わうことができたり、親族との会話を楽しむことができます。
結婚式を満足のいく仕上がりにしたいなら、ぜひウェディングテーブルを利用して理想の結婚式を挙げましょう。
この記事を書いた人
- 木幡
- Wedding table掲載のすべての結婚式場を現場でチェックしているトップコンシェルジュ。少人数・マタニティなどジャンルを問わず、自分たちらしい結婚式を挙げられるウェディングスタイルを提案。100以上の記事を執筆、監修。保有資格:「The Professional Wedding認定おめでた婚サポートプランナー」、マタニティの医療サポート認定資格「マタニティコンシェルジュ」










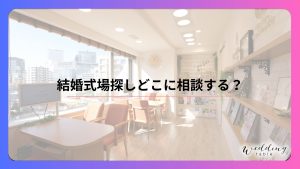


























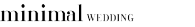







 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビル4F(ご来館の際は5階受付にお越しくださいませ)











